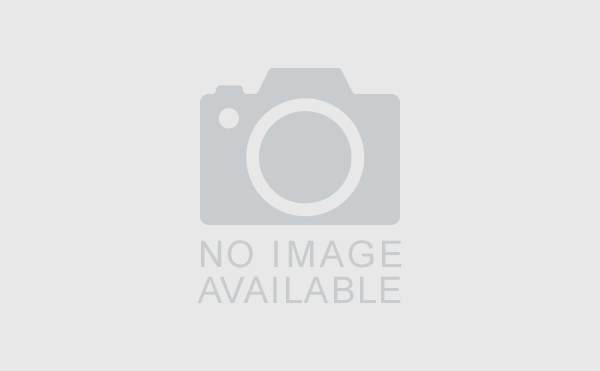相手に伝わり、心を動かす文章:アウトプットする
この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。
書く事は考えること。書くために必要なことを自分の頭で考える方法がわかれば、文章力が格段に進歩する。自分の頭でものを考えるための具体的な方法
よい文章を書くとは、どういうことか?
機能する文章を目指す
小論文の目指すゴールは「説得」だ。論理的思考力で評価される。小論文では、例えば、「問題提起→原因分析→解決の要件……」のように、論理的に思考を積み重ねることが基本だ。
働くために、生きるために、様々な必要や問題が生じ、そこに書く目的と読み手が生じる。状況に応じて、目的を果たすために、きちんと機能する文章の書き方を紹介します。あなたの書いたもので、読み手の心を動かし、状況を切り開き、望む結果を出すこと、それがゴールだ。
ポイントとなるのは、読み手の心を動かすことだ。読み手の心が動けば、何らかの形で状況は動き、結果が出る。だが、それは、自分の意のままに相手を操作することではない。書くことによって、あなたがあなたの潜在力を生かし、読み手を共鳴させることだ。読み手に、共感・納得・発見などの心の動きが生まれれば、やがてそれは読み手の内部で大きな振動となって、読み手自身の潜在力を揺さぶり起こすだろう。そういうふうに人に伝わる、人を揺さぶる文章を目指そう。
機能する文章を書くために考える7つの要件
機能する文章を書くために、何を考えていけばいいのだろうか?
1.意見
あなたが1番伝えたい事は何か?あなたが考えた、あなた自身の見解・意志を明確に打ち出すこと。
2.望む結果
誰が、どうなることを目指すのか?文章が機能した果てに紡ぎ出したい状況をできるだけ具体的に書くこと。
3.論点
あなたの問題意識はどこに向かっているのか?論点とは、文章を貫くあなたの問題意識だ。あなた自身と読み手、双方の問題関心から、ずれていない論点であること。また、問題意識が低いと、導き出す結果もそれなりになってしまう。文中にあなたが提起している「問い」は、良い価値を生むものになっていること。
4.読み手
読み手はどんな人か?望む結果を得るために、誰に書けば良いかを考え、最も適切な相手に向けて文章を書くこと。また、その読み手はどんな人かを知り、理解すること。どんな興味・問題関心・背景を持っているか、現在の状況はどうか。あなたの書くものは読み手に、興味を抱かせられるか、どんな意味があるか。読み手にフィットした内容である、もしくは読み手の個人差を超えた普遍的な内容であること。
5.自分の立場
相手から見たとき、自分はどんな立場にいるか?自分は相手からどのような人物と見られているか。信頼されているならば、文章は有効に働き、不信感を持たれていれば効力は低い。結果を出すためには、自分と言うメディアの信頼性・影響力を上げていかなくてはならない。初対面の相手や、自分との信頼関係がまだない相手なら、最初に相手との関係性をよくする内容や、自分というメディアの信頼性を示す自己紹介を加えるなどの工夫が必要だ。読み手から見た自分の見え方、立場を知り、それに応じた文章対策をすること。
6.論拠
相手が納得する根拠があるか?自分の主張の正当性を示す根拠が、しっかり道筋立てて述べられ、相手にとって納得のいくものになっていること。文章の説得力は「論拠」から生まれる。
7.根本思想
あなたの根本にある想いは何か?根本思想とは、文章の根底にある書き手の価値観・生き方・想いだ。文章を支える想いは、言葉に書かずとも如実に現れてしまう。
文章の基本構成
7つの要件のうち、実際に文章を書く上で、基本となるのが次の三要素だ。
1.論点:何について書くか。自分が取り上げた問題。
2.論拠:意見の理由。
3.意見:自分が1番言いたいこと。1に対する結論。
これは、日常で書くメモから論文まで、かなりの範囲カバーする文章の原則です。
自分が言いたいことをはっきりさせ、その根拠を示して、読み手の納得・共感を得る文章
字数や時間がない時、どこを残すか。最小単位は「意見」だ。文章で、最も重要なのは、あなたが1番言いたいこと、すなわち、あなたの意見である。意見のない文章は、「結局、何が言いたいのか?」ということになってしまい、文章として成立しない。
書くために、何をどう考えていくか?
意見:自分が1番言いたいことを発見する
意見とは何か?
意見とは、自分が考えてきた「問い」に対して、自分が出した「答え」である。「意見」のあるところ、必ず「問い」がある。その人の「問題意識」と言い換えてもいいだろう。
多くの場合、問いは無意識の中にある。正体不明の違和感、引っかかりを抱えて、ある日、ふと自分が何に悩んでいたのかに気づくことがある。
なぜ、意見が出ないのだろう?
自分の意見が打ち出せない原因
・考えていない
・大きすぎる問いを丸ごと相手にしている
・自分の根本にある思いに嘘をついている
・その問題に対する基礎的な知識・情報が不足しており、意見を理由資格がない
・決断によって生じるリスクを引き受けられない
などの理由が考えられる。
また、知らないことについて、意見は出せない。これは自然なことだ。不自然なのは、知らないのに意見を書いてしまうことだ。意見を求められても、自分が「よく知らない」ことを自覚し、意見を慎むという選択はできる。また意見しようと思うなら、必要なことを知り、調べてから責任の持てる範囲で書けば良い。見たり、聞いたり調べていくうちに、自分の見解は見えてくる。
自分の意見を発見する方法
言葉にならない心の引っかかり、胸のモヤモヤは、意見の種だが、そのままではいつか消えてしまう。意見を出すには、考えることだ。

参考文献
山田ズーニー『伝わる・揺さぶる!文章を書く』PHP研究所、2001年、236頁