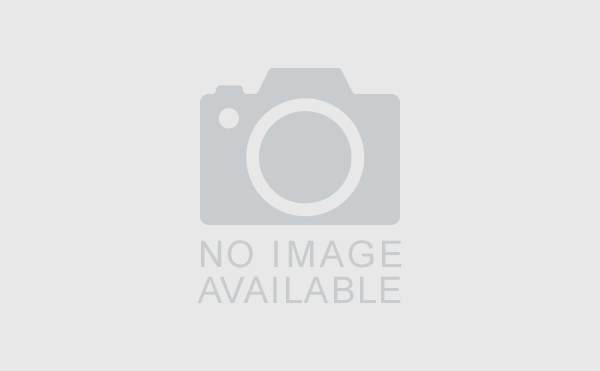ウォーキング
この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。
歩けば歩くほど健康になるという認識は大きな間違いです。運動のしすぎは健康効果がないどころか、健康を害することもあります。理由は、免疫力が低下するからです。
歳を重ねるほど、私たちは健康に対する様々な不安を抱えることになります。介護のこと、うつ病のこと、骨粗しょう症や骨折のこと、高血圧症のこと、糖尿病のこと、脂質異常症のこと、心筋梗塞などの心疾患のこと、脳卒中のこと、認知症のこと、癌など生活習慣病のことなど、健康に対する不安を数えれば、キリがありません。
こういったすべての病気に対して、ある指標に基づいたウォーキングが効果的であるということが研究を通じてわかってきました。
健康長寿を実現する黄金率
1日24時間の歩数= 8000歩
中強度の運動を行う時間= 20分
運動と病気の関係
① 4000歩/5分:要支援・要介護(特に寝たきり)の人がほとんどおらず、うつ病の人もほとんど見られない
② 5000歩/7.5分:要支援・要介護、うつ病ほとんどいない。認知症、心疾患、脳卒中の発症率が、これより身体活動の低い人と比べて圧倒的に下がる。
③ 7000歩/15分:要支援・要介護、うつ病、認知症、心疾患、脳卒中の人がほとんどいない。がん、動脈硬化、骨粗しょう症の発症率が、これより身体活動の低い人と比べて圧倒的に下がる。
④ 8000歩/20分:要支援・要介護、うつ病、認知症、心疾患、脳卒中、がん、動脈硬化、骨粗しょう症の有病率が低い。高血圧症、糖尿病の発症率が、これより身体活動の低い人と比べて圧倒的に下がる。
⑤ 10,000歩/30分:メタボリックシンドローム
歩き方を少し変えるだけで、日本人の死因第1位と2を占めるがんと心筋梗塞、生活習慣病の代表的な病気である糖尿病や高血圧症まで予防できます。
発症するたびに病気に対処するよりも、予防をしてしまう方が健康的で経済的ではないでしょうか。
人が病気になる原因
生活習慣
健康で長生きする人がいれば、病気で短命に終わる人もいます。
健康で長生きをした人たちがどのように過ごしたのか?
「中之条研究」とは?
群馬県中之条町に住む、65歳以上の全住民5000人の方々を対象に、24時間365日、10年にわたって生活の様子を調査した研究です。
ウォーキングには、量と質という2つの観点があります。量とはどれだけ歩いたか。質とはどれだけの強さで踏んだか。これが運動強度です。強度とは刺激のことです。重力に逆らって上下運動する際に起こる刺激が、骨密度の維持や筋肉量の維持に大きな影響を与えることがわかっています。
健康寿命が伸びる!中強度のウォーキングとは?
何とか会話ができる程度の早歩き。それがあなたにとっての中強度の運動です。
のんびり散歩のように、鼻歌が出る位の歩き方だと、ゆっくり過ぎます。(低強度)
強歩等のように会話ができないほどの歩き方だと早すぎます。(高強度)
運動強度を示す「メッツ(METs)」という単位があります。METsとは、「代謝当量」という意味です。音楽を聴いている時、読書している時、テレビを見ている時など安静にしている時が、1メッツです。1メッツの酸素摂取量は、年齢・性別にかかわらず、1分間に体重1キロあたり3.5ミリリットルと決まっています。
安静時の1メッツを基準に、何倍のエネルギーを消費するかで活動の強度を示します。最大20数メッツまであります。20数メッツは、マラソンのオリンピック・チャンピオンの数値です。
国立健康・栄養研究所が発表している「身体活動のメッツ表」

ほとんどの年代、特に中高年以降の年代の人にとって、早歩きこそが、中強度を代表する運動です。「何とか会話できる程度」の状態とは、息が楽すぎもせず、かといって、息苦しすぎもしない状態です。その状態が、「あなたの最大酸素摂取量の40〜60%程度」の目安であり、あなたにとっての「中強度」運動となります。
体温が1℃上がると免疫力は60%アップ
なぜウォーキングをすると健康になれるのか?一言で表現すれば、体温を理想的にできるからです。
理想的な体温を考える3つの要素
①平均体温
人間の平均体温は、乳幼児では37℃台と高く、成長するにつれ少しずつ下がり、10歳前後で一定の値に落ち着きます。ところが、高齢になると再び低下していきます。この平均体温の低下は、健康を大きく左右します。体温が下がると免疫力が低下し、病気にかかりやすくなるからです。
・平均体温が1℃上がると免疫力は約60%アップ
・平均体温が1℃下がると免疫力は30〜40%ダウン
平均体温は寿命・健康にとって非常に重要なものです。8000歩/20分ウォーキングは、脚などの大きな筋肉を動かすアクションです。細胞の代謝や体内の血流が良くなり、平均体温が上がります。
② 1日の体温推移
人間の1日の体温を調べてみると、決して一定ではありません。時間帯によって、体温が変化しています。若く健康な人の体温は低い順に並べると、①睡眠中、②起床時、③就寝時、②夕方となります。

若く健康な人の体温は、朝低いところから日中にかけて上がっていき、夕方の16時〜18時でピークを迎えます。そこから就寝に向けて体温は徐々に低下していきます。この体温の降下が我々に眠気をもたらし、快適な睡眠へと誘います。
睡眠に入ると体温はさらに下がり、午前4時前後に最も体温が低くなります。そして、朝目覚める少し前から体温を上げ、1日の活動に備えるのです。
歳をとると眠りが浅くなるのはなぜか?
図書を重ねたり、不健康になってくると、体温水は理想的なものと異なってきます。起床時よりも就寝時の方が体温が高いのが理想ですが、逆転してしまうのです。
理想とかけ離れた体温リズムで生活すると、不眠に陥りやすくなります。また、生活のメリハリもつきにくくなります。その結果、病気のリスクが高まってしまうのです。
青柳幸利『やってはいけないウォーキング』SBクリエイティブ、2016年、180頁